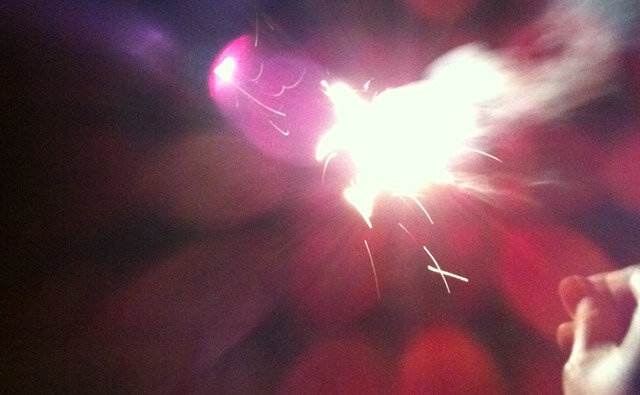第64回PHP賞受賞作
水野めぐみ
埼玉県・パート・50歳
実家を訪ねると、父がナスとキュウリと格闘していた。麻の皮を剥いだ芯の部分「おがら」を挿して足に見立て、牛と馬を作っている。精霊馬という、ご先祖様が行き帰りに使う乗り物である。
今年も盆入りだ。仏壇の飾り付けを終えた母が、盆提灯を手に畳の部屋から出てきた。
私も一緒に迎え火を焚くことにした。玄関先でおがらに火をつけ、ご先祖様が道に迷わぬようわが家の目印とする。「ようこそ、おいでくださいました」。母の声とともに、炎を盆提灯に移す。やわらかな光に心がほどけてゆく。ばあちゃんも無事に到着しただろうか。
私の父は東北の出身で、家は長兄が守っている。そのため、実家には母方の仏様がある。母は早くに両親を亡くし、残念ながら私は祖父母に会うことができなかった。祖父の死は37歳とあまりに若く、幼かった母の記憶はおぼろげだという。しかし、祖母との思い出はさまざまあるようで、母は祖母の苦労も間近に見てきた。
祖母は埼玉で生まれ育ち、東京下町の酒屋に嫁いだ。が、昭和20年の「東京大空襲」で町は壊滅的な被害を受ける。当時、母は生まれたばかりだった。店も家も失った祖母たちは、命からがら埼玉の実家へと逃げた。
食糧難の時代。嫁ぎ先の家族をみんな連れて帰ってきた祖母は、肩身が狭かったのか、夜になると一人涙を流していたという。そんな祖母に追い討ちをかけるような悲しみが襲う。夫と娘を、病で相次ぎ失ったのだ。娘とは母の姉で、まだ7歳だった。祖母は控えめで辛抱強かったというが、心痛はいかばかりだったか。想像するだけで胸がつまる。勤めに出て、帰って来ては畑仕事や家事を手伝う。そんな目の回るような忙しさが、ある意味、祖母の心を支えていたのかもしれない。
やがて母が成人し仕事に就くと、今の私の実家で母子水入らずの生活が始まった。慎ましくも、誰にも気兼ねしないおだやかな日々が、祖母には何よりの幸せだったようだ。
しかし喜びも束の間。ほどなくして祖母の体にガンが見つかる。耐えて耐えて耐えて。なぜ祖母の生きる道は、こんなにも険しいのか。53年の生涯。私は、母から祖母の話を聞くたびに胸が痛んだ。
「写真をお借りできませんか」
ところが、そんな沈む気持ちが救われる出会いが訪れる。私が中学生の夏休みのときだった。妹と二人、仕事に出ている母の帰りを待っていると、玄関先で「ごめんください」と大きな声が響いた。戸を開けると、見知らぬ白髪の男性が立っていた。男性は、ポカンと口を開けている私を見て微笑み、名乗った。そして、祖母と中学の同級生であること、この家を探すのに苦労したことを説明した。男性は歯科医で、最近になって息子さんに病院を託し、引退されたそうだ。時間ができたので、かつてのクラスメートを訪ね歩いているとのこと。祖母が10年以上前に亡くなったことを伝えると、とてもおどろいていた。
「では、写真をお借りできませんか」と言われて私は戸惑った。祖母の絵を描きたいそうだ。私は、ひとつ間をおいて答えた。「母が帰ったら、こちらからご連絡します」。
母に任せたほうがいい気がしたのだ。男性は自宅の電話番号を記したメモを残し帰っていった。夜、母の和やかな電話のやり取りを聞いて、写真をお貸しすることを知った。
祖母が笑顔で過ごした日々
ひと月ほど経ったころだろうか。あの白髪の男性が大きな荷物を抱え、再びやってきた。この日は、母と私と妹の3人でお迎えした。家にあがっていただき、母がお茶を出す。風呂敷包みからは、立派な油絵が出てきた。木々に囲まれた茅葺き屋根の家に、青い田畑。広がる萌黄色を背に、微笑む祖母と色鮮やかな菜の花。祖母の生家の風景だ。私たちが歓声をあげると、男性は当時の祖母の様子を静かに語った。「その場の空気を和ませる朗らかな女性だった。おだやかだがユーモアもあって親しみやすい。みんなに安心を与える存在だった」となつかしむように目を細めた。
祖母をほめてくださりうれしかったが、私の胸を熱くしたのは、祖母が笑顔で過ごした日々。母も喜び、笑ったり涙ぐんだり、忙しい。時を越えて、少女時代の祖母がいきいきとよみがえるようだ。実家のリビングでは、今も祖母が菜の花畑の真ん中で笑っている。
*
送り火の日は、とても暑かった。ご先祖様も道中大変であろう。「また、お越しください」と母がおがらを焼べる。ゆっくりと消えゆく炎を眺めながら、会ったことはないのに、ずっと前から知っているような祖母に想いを馳せる。私も、強くしなやかに生きられたなら、と思う。時の岸辺で、ばあちゃんを見送りながら。