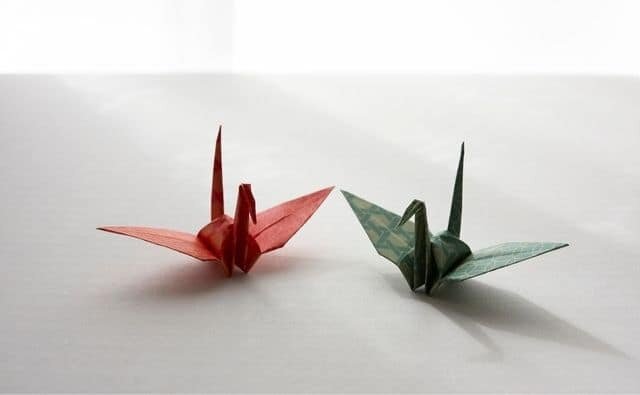父母は、遊ぶことが大好きだった。家に人を呼んで宴会をし、麻雀の卓を囲み、ドライブにでかけ、ダンスをした。こうやって書いてみるとわかるが、これらはほぼ子供と共におこなうことではない。かろうじてドライブは子供入りでできることだが、ドライブ自体が目的なので、行った先には子供むけのものは何もなかった。
結局わたしは子供時代、遊園地や海水浴や動物園などの遊興にはほとんど行ったことがなく、その楽しさも知らずに終わった。父母と共に過ごす時間でいちばん記憶に残っているのは、父母が家にお客を招いて麻雀の卓を二つつくり、徹夜で麻雀をするそのまわりでうろうろしていたことだ。たまにその中の夫婦連れが、わたしと同年代の子供を連れてくることもあり、かれらとは花札やカードゲームに興じたものだった。
そんな、子供むけではない日々が、ではいやだったのかといえば、それは違う。わたしは、子供の好む遊びが、少しばかり不得意だったのだ。高所恐怖症なので、遊園地のたいがいのアトラクションは怖いばかりだったし、海はしょっぱくて嫌いだったし、動物園の動物にはあまり興味がもてなかった。それよりも、麻雀をしている大人のうしろからパイをのぞき、「おとうふ......」とつぶやいて、「こらっ、何持ってるかわかっちゃうから黙ってなさい」などと叱られる方が、ずっと楽しかった。
小学三年生の時に、自分としてはいちばん優れた作文を書けたと自負した作品がある。それは、こんな始まりかたをしていた。
「『ポン』、うれしそうな声がひびく。
こちらでは、『赤たんそろった!』という声。」
会話文から始まる作文であり、二行目には体言止めもでてくる、三年生にしてはなんてかっこいい文章が書けたかと誇らしく思いながら提出し、花丸つきで返ってきたものを母に見せたら、青ざめられた。そして、こんなことは二度と書かないで、と頼まれた。本当のことを書いたのにと、少なからず不満だったが、母の意向は尊重して、その後作文では会話文始まりおよび体言止めはなるべく使わないようにした。
還暦を過ぎた今、子供時代をふりかえってみると、ありがたかったと思うばかりだ。父母が楽しそうだったから、わたしは何も慮る必要がなかった。父母の機嫌をとる必要もなかった。喜んでいるふりをする必要もなかった。いやなことははっきりいやだと言えた。のびのびと、育ってこられたことに、心から感謝している。ただ、小説を会話文で始める時と、体言止めを使う時には、今も一瞬心がちくっとするのですけれどね。
※本稿は、月刊誌「PHP」2020年6月号掲載記事を転載したものです。