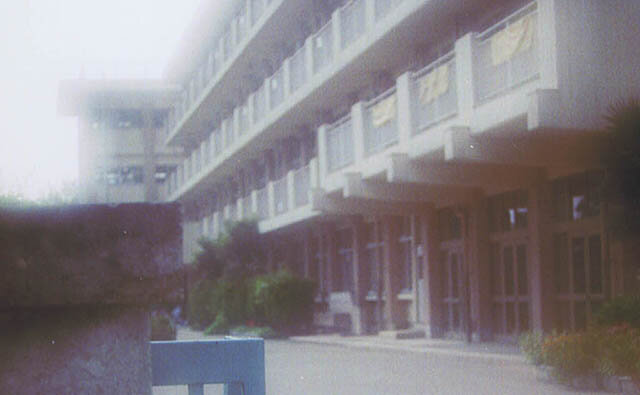第60回PHP賞受賞作
武藤光夫
千葉県袖ケ浦市・無職・六十六歳
しかし、いざ教師生活が始まってみると、理想と現実の差はあまりに大きいものでした。自信を持って生徒に指導できる教師に早くなりたいとは思うものの、焦れば焦るほど、力不足を痛感する日々が続いていました。
教師になって三年目、文化祭の学級劇の仕上がりでも、私の学級はほかの学級に大きく水をあけられる始末でした。
どんどん完成に近づいていくほかの学級。
自分の学級の大きな遅れに危機感を抱いた私は、とうとう日曜日に生徒たちを教室に集め、特別練習を行なうことにしたのです。
むかえた日曜日。私は、はやる気持ちを抑えきれず、集合時間の一時間も前に職員室に到着しました。前日に確認した学級劇のクライマックスの場面の台本を何度も読み返し、生徒たちの登校を待ちわびていました。
そのときでした。静かな職員室にけたたましい電話のベルが響きわたったのです。
急いで受話器をとると、聞こえてきたのは、「助けて」と叫ぶ、妻の声でした。一歳になったばかりの我が子が誤ってトイレの内鍵を閉め、中に閉じ込められて大泣きしているというのです。
妻の尋常ではない叫び声に、私の心は大きく揺り動かされました。
自宅に戻らねばと焦る気持ちの一方、時計に目をやれば、生徒たちとの約束の時間も刻一刻と迫っています。
(遅れに遅れている学級劇の練習を中止にすることなど、とてもできない。でも、もし今家に戻れば、往復するのに一時間以上はかかってしまう。どうすればいいんだ......)
妻のオロオロする姿、トイレで泣き叫ぶ我が子の姿、そして、生徒たちの姿が私の頭の中をぐるぐると駆け巡りました。
生徒たちの冷たい目
気づいたときには、私は自宅に向かって、夢中でアクセルを踏み続けていました。生徒たちと交わした約束の時間には、とても戻ってくることはできないと思いつつ......。
祈るような気持ちで自宅に向かい、何とか我が子をトイレから救出した私は、急いでまた学校へと戻りました。
しかし、校門で待っていたのは、氷のように冷たい目で私をにらむ生徒たちの姿でした。
「休みの日に朝早くから生徒を学校に集めておいて、自分は遅刻かよ。バカバカしい」
そんな捨て台詞を残し、怒りをあらわにして帰り始める生徒たち。覚悟していたとはいえ、結局一時間以上も待たせてしまった私は、帰っていく生徒たちに遅れた理由すら話すことができませんでした。
次の日から、地獄のような日々が続きました。朝のホームルームでも、授業や給食の時間でも、生徒たちは無視を決め込み、私が教室にいることすら拒んでいるようでした。その空気の重さは、とても耐えられるものではありませんでした。
追い詰められた私は、もう自らの行動で誠意を示していくことしかできません。文化祭までの残りわずかな時間、何とか生徒たちを支えようと、黙って準備を進めました。
生徒たちに学ばせてもらおう
いよいよ明日が本番という文化祭前日のことです。
最後の練習を終え、生徒たちが下校した後、私は一人教室に残って、机とイスをもとの位置に戻していました。
すると、いつやってきたのか、学級のI君が教室の扉から、半分だけ顔を出していました。彼はこう言いました。
「先生、みんな言ってたけどさ、本当はあの日、何か訳があったんじゃねえの?」
思いがけないI君の言葉を耳にした瞬間、私の目から大粒の涙がこぼれ落ちました。
私を気遣ってくれた彼の言葉がたまらなくうれしかった。そしてほかの生徒たちも、「きっと何か訳があったにちがいない」と私の事情を考えてくれている。そのことが言葉にできないくらいありがたかったのです。
「そうだと思ったよ......」
I君のとりなしがあったのか、文化祭当日、教室に現れた生徒たちには、明るく元気な笑顔が戻っていました。
学級劇本番での、生徒たちの生まれ変わったような演技を見ながら、私の心もまた一変していました。
(私は、生徒たちに自信を持って指導できるような教師に早くなりたい、などという考えを持っていた。けれど、これからは生徒たちのあの美しい心に、もっともっと謙虚に、いろいろなことを学ばせてもらおう。そんな教師に必ずなってみせる!)
私の教師としての生き方が大きく変わったのは、間違いなくあのときでした。